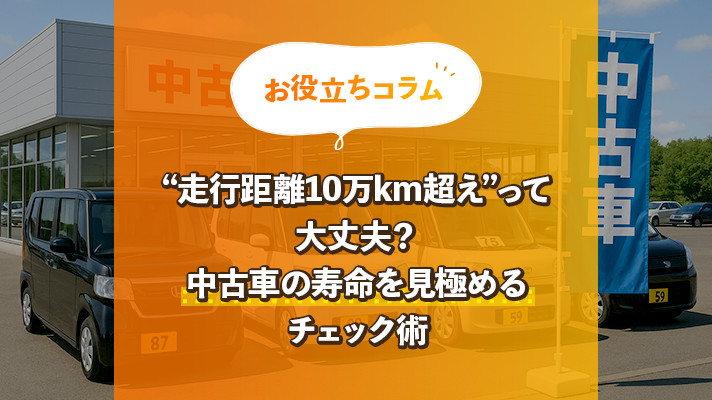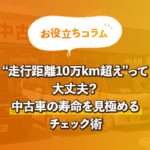中古車を探していると、「走行距離10万km超え」という車を目にすることがありますよね。
「価格は安いし良いけど、そんなに走ってて大丈夫?」と不安になるのも当然です。
ですが、適切に整備されていれば、10万kmを超えていてもまだまだ現役で活躍できる車はたくさんあるんです!
なぜなら車の寿命は“走行距離だけ”では決まらないからです。
このコラムでは、走行距離に惑わされず、車の「本当の寿命」を見極めるためのポイントを解説します。
このコラムは
1.自動車整備の基本的な点検内容(参考例:JAF、日本自動車整備振興会、整備士向け教本)に基づくもので、走行距離よりも機関の状態が重要であること。
2.中古車業者では公式に「整備記録簿あり」の車両が優良中古車として取り扱われるケースが多く、その記録が残っていること自体が信頼性の指標となること。
3.カーセンサーや Goo-net、中古車査定業者のデータ、ならびに国内外の自動車長寿ランキング(米国「iSeeCars」など)から、日本車が20万km以上耐久するケースが多いことを根拠としています。
01. 「走行距離=寿命」じゃないってホント?
よくある誤解のひとつが、「10万kmを超えると、車はもう終わり」という考え方。
でも実際には、定期的にメンテナンスされてきた車なら20万km以上走ることも珍しくありません。
例えば、タクシーや配送車などは30万km以上走ることもありますよね。
これはしっかり点検・整備されているからです。
■ 例え話
車を“人間の体”に例えると、走行距離は「年齢」にあたります。
でも年齢だけでは健康状態はわかりませんよね?
毎年健康診断を受けて、運動もして、きちんと栄養をとっていた人の方が、若くても不摂生な人より元気、なんてことは普通にあります。
車も同じで、大切なのは「どう乗られて、どう整備されてきたか」です。
02.まず見るべきは「エンジンとミッション」
車の“心臓”であるエンジン、そして“神経系”のような役割をするミッション(変速機)。
この2つの調子が良ければ、車はまだまだ元気です。
■ エンジンのチェックポイント
・エンジンをかけたときの音がスムーズか?
・ブルブルとした振動が激しくないか?
・白い煙や黒い煙がマフラーから出ていないか?
・アイドリング(停車中)で音が不安定じゃないか?
特にAT車の場合、ギアが滑る感覚や異常なタイムラグがあれば要注意。
整備記録が確認できる場合は、オイル交換や整備履歴も要チェックです。
■ ミッションのチェックポイント
・シフトチェンジがスムーズか
(「ガクッ」と衝撃がある、加速がもたつくなどは注意!AT・CVT・MT共通)
試乗できる場合は必ず走ってみるのがおすすめです。
03.「整備記録簿」は車の“健康診断書”
中古車選びで重要なのが、「メンテナンス履歴(整備記録簿)」の有無です。
これは車が過去にどんな点検や修理を受けてきたかを記録したもの。
例えば、
・エンジンオイルは1万kmごとに交換されていたか?
・タイミングベルト(またはチェーン)は交換済みか?
・ブレーキパッドやバッテリーはいつ交換されたか?
10万km以上の走行距離でも定期的なメンテナンスを受けてきた車は、5万kmしか走っていなくてもメンテナンス不足の車より、はるかに良い状態を保っていることがあります。
整備記録がしっかり残っている車両は、それだけ丁寧に扱われていた証拠になります。
■ ワンポイント:こんな販売店は要注意
・記録簿が「ある」と言いながら見せてくれない
・「現状渡し(ノークレーム)」の表示がある
(現状渡し:納車前に整備や部品交換はしないということ。ノークレーム:クレームを受け付けません、という宣言のことです。)
こういったケースは避けた方が安心です。

04.「長寿命な車種」を選ぶのも賢い選択
同じ10万kmでも、「タフな車」と「不具合が出やすい車」があります。
ここで言う「タフな車」は国産車、「不具合が出やすい車」とは輸入車をさします。
ですが、間違ってはいけないのが輸入車が壊れやすい、という意味ではないということ。
ではなぜ違いが出るのか?それには設計思想と整備前提の違いが関係しています。
■ 日本国内メーカーがタフとされる理由
【設計思想】
・誰でも安心して使える「壊れにくさ重視」
トヨタ・ホンダ・日産・スズキなどの国産車は、過酷な環境(雪国、暑さ、短距離運転など)で“メンテナンス頻度が低くても壊れにくい”ことを前提に作られています。
【整備前提】
・部品供給のコストが安定している
部品調達や修理コストは、ディーラー網が全国に整っており安く済むことを前提にしています。
■ 輸入車に不具合が出やすいとされる理由
【設計思想】
・定期的な整備が前提
メルセデス・BMW・アウディ・プジョーなどの欧州車は、定期的な整備(特に専用診断機や純正部品)を前提に作られています。
エンジン性能や走行性能が高く、質感や快適性も上ですが、輸入車に慣れていないユーザーが「国産車と同じ感覚」で乗ると、維持費がかさむ=壊れやすいと感じてしまうというわけです。
【整備前提】
・部品供給のコストは高騰しがち
修理のたびに純正部品が高額になりやすく、工賃も輸入車対応の店舗でないと高くなりがち。
車検や点検時の費用に関しても、日本車より高額になるケースが多くあります。
■ 自分のライフスタイルにあった車を選ぶのがポイント
忙しい現代、デザインやメーカーだけでなく、目的にあった乗り方ができるか?頻繁にメンテナンスができるか?など、購入後の維持費も考慮しての車選びがポイントです!
05.走行距離より大事なのは「バランス感覚」
中古車の走行距離は「距離が短ければ安心」「長ければ危険」と決めつけるのではなく、
✔ 整備状態
✔ 年式(古すぎないか)
✔ 使用環境(雪国/海沿いなど)
など複数の情報を総合的に判断することが大切です。
【整備状態】
01、03の項目で書いた通り、定期的にメンテナンスされた車は走行距離が多くても良いコンディション・まだまだ現役の場合が多いです。
【年式】
時間は“劣化”のもう一つの軸です。
走っていなくても、ゴム部品や配線、内装・塗装などが経年劣化していき、整備では完全にカバーできない部分です。(交換が可能でもコストが高くなる、診断が難しいのが難点)
【使用環境】
車の“使われた場所”によって、見えない劣化の進み具合が変わります。
・雪国で使われていた車
塩カル(融雪剤)による下回りのサビ進行が早い
マフラーやフレームが腐食している可能性あり
・ 海沿い地域で使われていた車
潮風によるサビ・腐食リスクあり(塗装や電装にも影響)
(表面のサビは処理可能だが、内部の腐食進行は止められず完全な防止は不可能)
■ まとめ
整備をしっかりしていれば「走行距離や劣化の進行を遅らせる」ことは可能ですが、年式や環境由来の“時間と素材の限界”は完全には取り除けないのが現実。
そのため、「整備記録+年式+使用環境」すべてのバランスをみて判断することが重要になります。

06.まとめ
<10万km超えの中古車は“選び方”次第で大当たりもある!>
初めてや慣れなていない方の中古車選びは、不安でいっぱいかもしれません。
ですが、10万kmを超えた車でもしっかり整備されていて状態が良ければ「価格は安く、寿命もまだ長い」というコスパ最強の1台になり得ます。
数字だけで判断せず、プロのアドバイスも受けながら、“状態重視”で中古車選びをしてみてくださいね。